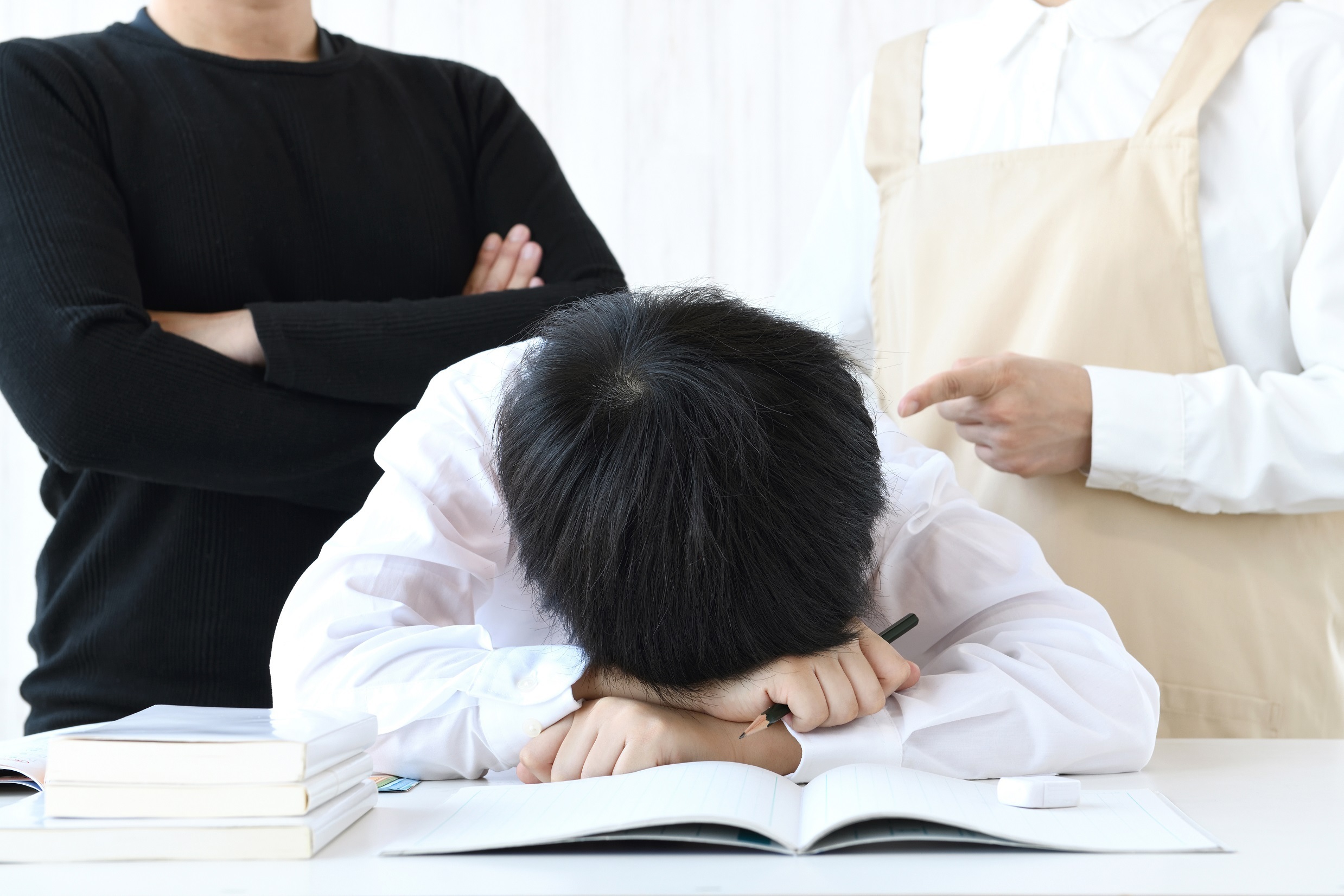「ダブルバインド」という言葉を知っていますか?実は子育てに一生懸命なママパパほど注意が必要です。「ダブルバインド」の意味を知り、子どもとの関わり方を見直してみましょう。大人の言動が変われば子どもの姿も変わっていきます。
子育てにおける「ダブルバインド」とは

ダブルバインドという言葉の直訳は、
「二重拘束」です。相反する言葉や態度、表情で人に接することを表現する言葉として、最近使われるようになりました。
子育てにおける「ダブルバインド」とは、相反する態度や言葉を親が子どもに向けることを指します。
例えば…
●言葉では「OK」のメッセージを出しているのに、表情では「NG」のメッセージを送る
●言葉では「OK」のメッセージを出しているのに、実際子どもが行動したらNGの反応をする
●子どもの望ましい行動を引き出すために、実際は行動にうつさない言葉をかける(子どもが怖がる言葉を使う)
親は言うことを聞かせるため、無意識に子どもに強い言葉を使ってしまうことがあります。なかなか思い通りに動いてくれない子どもを行動させるために、即効性のある言葉を使いたくなるからです。
親が子どもに言うことをきかせようとするのは、多くの場合、子どものためを思ってのことです。親が信じている「正しい」価値観を伝えようとするからです。
しかし
伝え方を間違えると「ダブルバインド」になってしまい、子どもの育ちを歪めてしまう危険をはらんでいます。
親がやってしまいがちな「ダブルバインド」の例
それでは具体的にどんな例が考えられるのでしょうか?子育て中にやってしまいがちなダブルバインドをご紹介します。以下を参考に、普段の言動をチェックしてみましょう。
【未就学児】ダブルバインドになるフレーズ
☑ 先に帰っちゃうからね
☑ 片付けないなら捨てちゃうよ
☑ 小学生になれないよ
【NGポイント解説】
「先に帰っちゃうからね」
親が帰りたくても、子どもが遊び続けてなかなか帰れないと、つい使ってしまう言葉です。「先に帰っちゃうからね」と言えば、子どもが「やだ〜」と追いかけてくることがわかっています。もし子どもが追いかけてこなかった場合、子どもを置いて先に帰ってしまうことはできません。子どもは割と早い段階でこの事実に気がつきます。
「片付けないなら捨てちゃうよ」
いくら言っても子どもが部屋を片付けないとき「片付けないなら捨てちゃうよ」と伝えたくなります。捨てられたくない一心で片付けるからです。しかし実際に捨てることは少ないでしょう。多くのものは親が必要だと思って購入したものだからです。
「小学生になれないよ」
「小学生になれないよ」は、年長組に属する子どもに言いがちな言葉です。「小学生になりたい」「小学生になれないと嫌だ」という子どもの気持ちを利用して、行動を促します。しかし親の言葉とは関係なく、4月になれば6歳の子は全員小学生になれます。6歳くらいになると「みんな小学生になれる」ということに気がつく子が増え、親の言葉は効力がなくなります。
【小学生】ダブルバインドになるフレーズ
☑ 好きなものを選んでいいよ
☑ 勝手にしなさい
☑ 怒らないから言ってごらん
【NGポイント解説】
「好きなものを選んでいいよ」
スーパーのお菓子コーナーで「好きなものを選んでいいよ」と言います。親としては100円くらいのお菓子を想定していたつもりでも、子どもは500円くらいの大袋を持ってくるかもしれません。「大きいのはダメ、他のにしなさい」と言われれば、子どもは「好きなものって言ったのに」と感じることでしょう。
「勝手にしなさい」
子どもが危険なことをしていたり、社会的によく見られない行動をしていたら親は止めます。しかし子どもは親の制止を振り切ることがあります。
親が止めても言うことを聞かない場合によく使う言葉が「勝手にしなさい」です。
実際には勝手にされたら困るので、別の形で行動を止めたり、叱ったりすることになります。
「怒らないから言ってごらん」
「怒らないから言ってごらん」は、閉口している子どもから言葉を引き出すときに使う言い方です。「怒らないから言ってごらん」と言っている表情がすでに怒っている、というのはよくあることですね。また、子どもが意を決して本当のことを言ったら、やっぱり怒られた…というのもダブルバインドになります。
【中学生】ダブルバインドになるフレーズ
☑ やる気がないならやめたら?
☑ 好きにしなさい
☑ ママ「お風呂入りなさい」パパ「勉強しなさい」
【NGポイント解説】
「やる気がないならやめたら?」
「やる気がないならやめたら?」は、子どものやる気を引き出そうとして使う言葉です。中学生だと勉強や運動に対して使われることが多いでしょう。
「勉強する気がないなら、塾やめたら?」「スタメン入りする気がないなら、部活やめたら?」と親は喝を入れるつもりで言います。しかし実際に「じゃあ、やめる」と子どもが言ったとき、本当にやめることを許容するならよいですが、「何バカなこと言ってるの」とやめさせる気がなかった場合はダブルバインドになります。
「好きにしなさい」
中学生になると友だちが増え、世界が広がるため、子どもは親に意見するようになります。返す言葉がみつからなかったり、言い合いに疲れてしまったりすると「好きにしなさい」と言ってしまうこともあるでしょう。
しかし、実際には好きにさせられないことも多々あります。身体は大きくなっても、まだ自分の行動に責任がとれないからです。
ママ「お風呂入りなさい」パパ「勉強しなさい」
最後は親2人によるダブルバインドです。ママは「お風呂に入りなさい」と言っているけど、パパは「まずは勉強しなさい」と言っている場合、どちらの意見を優先していいのかわからず、子どもは混乱してしまいます。とくに夫婦仲がよくない場合、子どもはバランスをとろうとして、どちらの意見を選ぶこともできません。
ダブルバインドの言動が引き起こす子どもへの影響
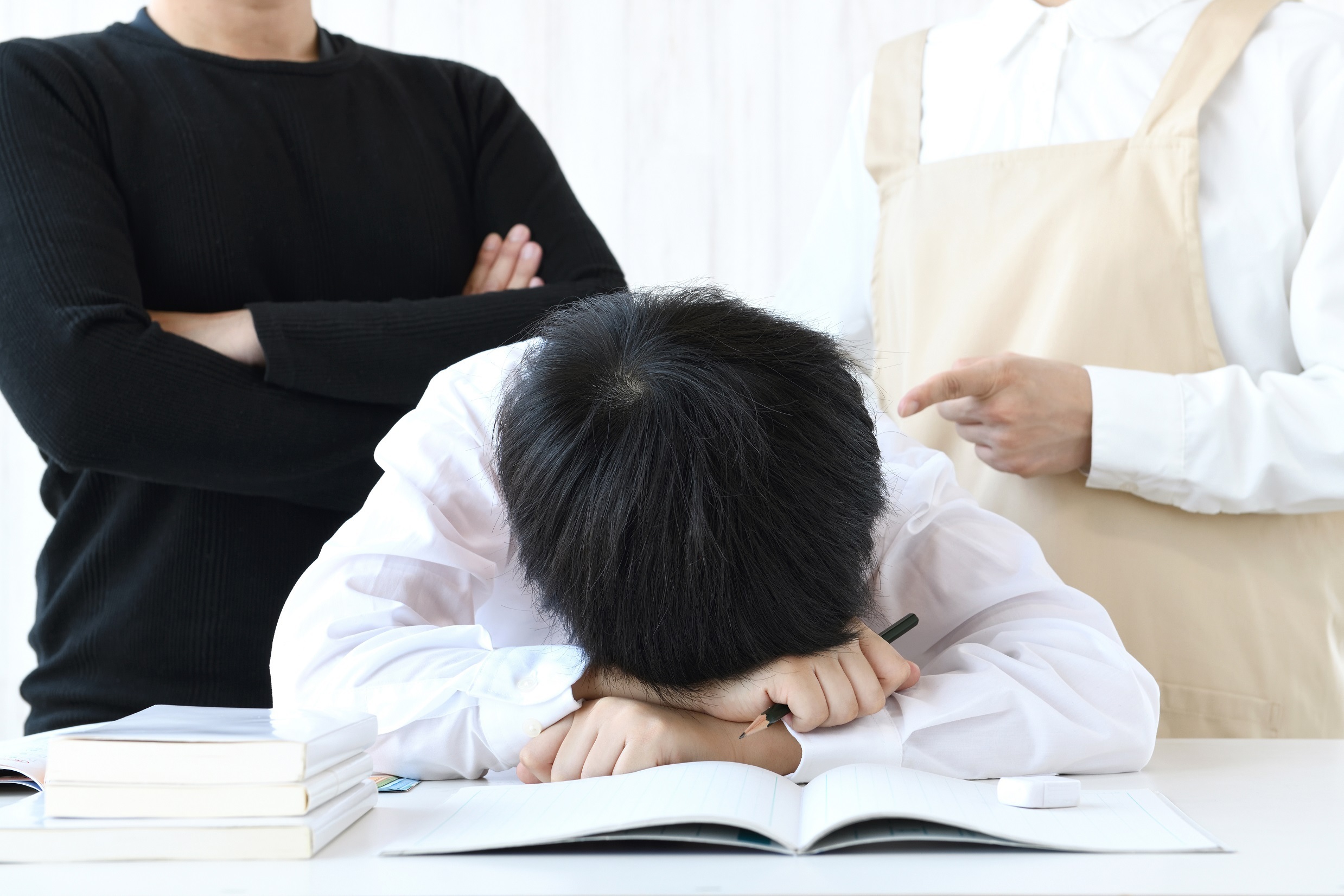
日常的にダブルバインドのやり取りが続くと、子どもにどのような影響があるのでしょうか。保育士の観点から解説します。
子どもの心への影響
ダブルバインドが続くと、まずは子どもの心に以下のような影響が出ます。
●不安を感じる
●親を信用できなくなる
親が子どもの行動をコントロールするために「置いていくよ」「もう知らない」などの言葉を使うと、子どもは親に「見捨てられてしまうかもしれない」という強い不安を抱くようになります。
子どもにとって親は自分を守ってくれるとりでです。
「親に見捨てられないようにしなきゃ」と思いながら過ごすのは、子どもの心を疲弊させます。
経験を重ねると「親の言う通りにしなくても見捨てられない」ということがわかってきます。しかし同時に親の言葉を信用できなくなります。
親の言葉に重みがなくなり、「そうは言っても、本当は違うんでしょ」と親自身を信じられなくなってしまいます。
子どもの発達への影響
子どもが親の言動を素直に捉えられないことで、発達に影響が出る可能性があります。生きる力を育む上で重要な「自己肯定感」「自主性」「自己決定力」が失われることも考えられます。これらは、子どもが自立して生きていくための土台となる力です。大切な3つの発達がどのようなものか、説明します。
◆自己肯定感
自己肯定感とは「自分のことを大切に思う気持ち」です。他人からの評価ではなく、自分で自分をプラスに評価する力があることで、物事に前向きに取り組むことができます。
◆自主性
自主性とは「やってみようと思える気持ち」です。「やってみたい」と思ったら、自分で行動に移すことができる力です。もし間違ったり、怒られたりしても、心の根底で自分が愛されていることを知っていると、失敗を恐れずに挑戦し続けることができます。
◆自己決定力
自己決定力とは「自分で選択できる力」です。生きていくことは選択の連続です。自分の選択で間違っていたと気づいたら、自分で行動を修正していくこともできます。
上記3つの力は目に見えないですが、子どもが成長する上で、大切に育みたい力です。そのためには、子どもが不安を感じるダブルバインドを避ける必要があります。
子どもの行動への影響
子どもが年齢に沿った適切な発達ができないと、行動にも影響が出ることがあります。小さいうちは見捨てられないよう、ママパパの言葉に従うでしょう。しかし、大きくなるにつれて以下のような行動をする可能性があります。
●自己主張しなくなる
●自分より弱い立場の人を脅すようになる
●親の価値観に合わせて生きようとする
●親の目を気にして行動するようになる
●親が怒りそうなことを親に隠れてする
これらの姿は、ママパパが望んでいる子どもの姿とは異なるのではないでしょうか。自信をもって人生を選択し、自分の足で立っていける大人に育てるためには、ダブルバインドにならない言動の中で育てることが重要になってきます。
ダブルバインドにならない子どもとの会話の仕方
親自身が成長の過程で受けとってきた言葉を、自分の子どもにも使ってしまう可能性もあります。そのような場合はダブルバインドになってしまっていると気づいても、他にどう声をかけたらよいのかわからないですよね。
そこでここでは特に小さな子どもに対してのダブルバインドにならない会話例をご紹介しますので、実際に接する際の参考にしてみてください。
【会話例1】はじめに条件を伝える
子「お菓子、買って〜」
親「100円以内でガム以外のお菓子だったらいいよ」
子「わかった。選んでくる!」
子どもの行動を予想して、事前に条件を伝えましょう。
【会話例2】選択肢を提示する
子「お菓子、買って〜」
親「Aのお菓子か、Bのお菓子、どちらかだったらいいよ。」
子「じゃあ、Aにする!」
選んでほしくないものは選択肢にあげないことがポイントです。
【会話例3】気持ちを受け入れて、ダメな理由を説明する
子「どうしてもCのお菓子がいい…」
親「Cのお菓子が好きなのね」
子「うん」
親「どうしてCのお菓子がいいの?」
子「だっておいしそうだもん」
親「そうだね。でもちょっと高いから、今度特別なときに買おうね」
子「今度おばあちゃんが遊びにくるときは?」
親「いいね。そうしようか」
時には子どもの希望に添えないこともあります。子どもの気持ちを受け入れながら、ダメな理由を説明しましょう。頭ごなしに否定したり、曖昧な態度でダブルバインドにしたりしないことが大切です。
子どもが言うことを聞かない…そんなときの親の心得

子どもが言うことをきかないとき、つい「もう知らないからね」と見捨てるような言葉を使ってしまいますよね。それは、その方が手っ取り早いからです。しかし
ダブルバインドの言葉では、子どもの育ちを歪めてしまいます。子どもの態度や行動の方をすぐに変えるのは難しいので、ここはまずママパパの考え方を少しだけ変えてみましょう。
【親の心得1】子どもの成長を信じてみる
子どもの成長を信じましょう。さまざまな経験から子どもなりに学び、育っていきます。子どもは親の思う通りには動きません。言うことを聞かせようとすればするほど、子どもは心を閉ざしていきます。子どもの声に耳を傾け、コミュニケーションを大切にしながら、子どもの成長を支えていくことを心がけてみてください。
【親の心得2】子どもへの気持ちの伝え方を工夫する
子どもの成長を信じるからといって、親が口を閉ざせばよいわけではありません。親が自分の気持ちを我慢したところで子どもにはそれが透けて見えるため、結局はダブルバインドになります。
それを回避するために、
親も自分の素直な気持ちを表現しましょう。伝えるときのポイントは、主語を「わたし」にすることです。「ママは〇〇だと思うな」「パパは〇〇してくれたら嬉しい」と、自分の素直な気持ちを伝えましょう。
この時注意しておきたいのは「親と子どもの考えは違うかもしれない」ということを忘れないことです。もし親の気持ちに沿わなかったとしても、それも子どもの成長だと思って受け止めましょう。
【親の心得3】子どものありのままを認める
生まれてきたときは「元気で幸せに大きく育ってくれたら……」と願っていたはずなのに、子どもが大きくなったら親は色々なことを求めてしまいます。
原点に立ち返り、子どものありのままの姿を認めましょう。
子どものありのままを…といっても、安全面だけはしっかり守らなくてはいけません。大怪我や取り返しのつかない事故の危険は親が取り除くようにしましょう。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
子どもとの接し方に悩んだら、保育のプロの力を借りよう

本来は「ちゃんと育ってほしい」という親の思いが、知らず知らずのうちにダブルバインドにつながってしまっていることもあります。しかし
親の言動が子どもの力を奪ってしまっているのだとしたら、対応を変えていく必要があります。
とはいえ、これまで築いた子どもとの関係性を、いきなりリセットするのはなかなか難しいでしょう。そんな時は保育士や
ベビーシッターなど、保育のプロに相談するのもオススメです。
保育のプロは、子どものよいところを見つけてくれたり、子どもへの声のかけ方を教えてくれたりします。また、第3者に子どもを見てもらうことで、親自身が客観的に子どもの姿や良さに気付くという利点もあります。
ついつい発言がダブルバインドになっている時は、親の方も仕事や育児に追われて疲れがたまっているということも考えられます。安心して任せられる保育のプロに少し子どもを預けて、親としての本来の思いに立ち返ってみる時間を作ってみるのも1つの手です。
子どもの力を素直に信じられるようになれば、ダブルバインドとなる言動も減り、子どもとのやりとりを心から楽しめるようになるはずです。子育ては長丁場なので、方向が違った時は修正しながら、無理せずに子どもとの日々を大切に過ごしていきましょう。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
キッズラインには、家庭保育のプロが在籍
ベビーシッター・家事代行サービスのマッチングプラットフォームであるキッズラインでは、
ベビーシッターとして、保育士や看護師など保育の専門資格や研修を完了した家庭保育のプロフェッショナルが多数在籍しています。
初めてのシッターに保育を依頼する際には、顔合わせまたは事前面談が必要なので、まずはよさそうな人に連絡を取ってみましょう。子どもと接する際に「ダブルバインド」になりがちなことなどを話してみて、子どもの様子を見てくれたベビーシッターに助言を仰いでみるのもオススメです。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
■保育士ライター 佐野希子
18年目の現役保育士。独学で認定試験に合格し、幼稚園教諭の資格も取得。他に社会福祉士の資格も保有。現在は副主任として保育現場の指導とサポートに努めている。
▼あわせて読みたい
子どものほめ方がわからない!ベテラン保育士のノウハウを伝授
朝の支度が進まない!子どもが自ら動いてくれる声かけのコツとは【保育士監修】
子どもが登園拒否!「保育園に行きたくない」の理由と対処法
▼記事一覧に戻る
KIDSLINE編集記事一覧
▼TOPページに戻る
KIDSLINE TOPページ