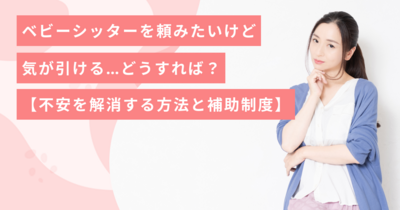「パタハラ」というキーワードが話題になり、共働き世代の子育てのあり方が議論になっています。共働き世帯はこの40年で専業主婦世帯の約2倍になり、父親も母親も、子育てと仕事の両立が求められる時代です。
こうした「共働きスタンダード時代の育児」をテーマに、キッズライン代表の経沢とジャーナリストであいちトリエンナーレ2019で芸術監督をつとめることでも話題の津田大介さんの対談が実現しました。
津田大介:ジャーナリスト/メディア・アクティビスト。ポリタス編集長。1973年生まれ。東京都出身。早稲田大学社会科学部卒。早稲田大学文学学術院教授。メディアとジャーナリズム、著作権、コンテンツビジネス、表現の自由などを専門分野として執筆活動を行う。
「家計を支える母」「家事をする父」の共働きが原点
経沢:今日はよろしくお願いします!津田さんがあいちトリエンナーレ2019の芸術監督をつとめられて「ジェンダーギャップ」をテーマにされたことが対談のきっかけになりました。
いきなりですが、津田さんは現在独身ということですが、どんな女性をパートナーにしたいですか?
津田:僕ですか(笑)⁉︎ …(照れながら)…自分を持っている女性が好きですね。
経沢:じゃあ、結婚しても出産しても働きたい女性でしょうか?
津田:え~っと(汗)。僕のジェンダー観は、僕の家庭環境がすごく大きいと思います。僕の両親は、共働きなんですね。
父親はお金を稼ぐよりも思想に生きた人。母親は公務員でした。だから、母が家計を支えている構図ですね。でも、母親は病気がちだったので、父親が家事などをかなりやっていたんです。
この経験は、決定的に僕の仕事観やジェンダー観を支えています。だから、共働きは僕にとっては自然なことで、それが女性のタイプにつながっているんでしょうね。
「男子校に女子が入学するのは難しい?」
経沢:誤解を恐れずにいうと、私の体感ですが「社会は男性向けにつくられてきた」ということです。だから、企業の上層部の人は「女性を採用した方がいい」と頭で理解しても、男子校を女子校にしていく、みたいな感じで難しくてなかなか進まない。
でも、「女性が活躍している会社の利益率は高い」などと経済合理性を指摘すると、男性も動く印象です。
津田:今年出版された『WORK DESIGN行動経済学でジェンダー格差を克服する』という本でも、その議論があります。著者は、ハーバード大学ケネディ行政大学院の行動経済学者イリス・ボネット教授という女性で、経済学の学部長まで勤められた方です。
その中で「マクロレベルでもミクロレベルでも女性をどんどん活用する方が、経済にはいいことがわかっている」と述べているんですね。
この本では女性活用と経済の関係性についてのデータが豊富に紹介されているのですが、ただ注意したいのは、「経済合理性にかなうから女性の活用を増やした方がいいんだよ、という議論は危険だ」と言ってるんです。
経沢:そうなんですか⁉︎
津田:女性を増やしたら必ず経済的に成長する、という因果関係があるわけじゃないからです。データはあくまで補強材料に使うだけで、男女平等を実現した方がいいのは「道徳的に正しいからなんだ」と。
僕自身も「あいちトリエンナーレ2019」の芸術監督として、女性作家に光を当てて起用するなどジェンダーギャップに取り組んでいると、世間からは「女性のためにやっているの?」といわれます。でも、違います。道徳的に正しいからやるんですよ。
平等が正しいということには、議論の余地がないのです。
経沢:なるほど。でも、私は道徳的のみならず、一人一人がしあわせになるためには、選択肢が増えることがすごく重要だと思っています。
津田:僕も、専業主婦とワーキングマザーの間で、争いごとは不毛なので起こすべきじゃないと思います。女性同士の争いが起きて得をするのって、男性しかいないから。特に経営層(笑)
経沢:ほんとだ!(爆笑)
ロールモデル不在でも、能力の生かし方がマッチングすれば月商100万円を実現できる
津田:経沢さんの「一人一人が幸せになるためには、選択肢が増えることがすごく重要」だという話はポイントです。これまでは男性社会の構造で、女性の選択肢がなかった。それが、増えてきている。
キッズラインのベビーシッターさんで、元専業主婦から月商100万円も稼ぐ人が出てきていますね。僕、ほんとに素晴らしいと思っています。マッチングができれば、家の中でしか生かすことができなかった職能で、大きな経済的な価値を生むことができる。これもある種のシェアリングエコノミーですよね。
経済的に自活できる手段が増えることは女性の自信にもつながりますし、社会にまた戻っていける。選択肢が無限に増えていく取り組みです。
女性はロールモデルがなかなかいないんですよね。すべてのシングルマザーが、経沢さんみたいになれる訳ではないし(笑)。だけど、「ここをちょっと真似しよう」とか「この人は何%参考にしよう」とか、ロールモデルの多様化が大事だと思うんです。
経沢:一人一人の選択が尊重されて、自分のやりたい事を追求できる社会になってほしい。みんなが合理的でフラットな器の大きな社会になればいいなと。
津田:質の基準をいじらず男女比を正すには、「ロールモデルを作る」ためにも女性に光を当て続けるということも大事でしょうね。
育児もテクノロジーを活用した上で「わたしはどう生きる?」を問う時代
経沢:子どもを持った後も「自分の人生を継続していく」という仮説を持つなら、積極的に子育てをシェアしていく! ということがすごく重要だと思います。
同じ24時間の中でフルに自分で稼働できる人と、子どもを持つ人で有利・不利の差が出るという話になるんです。もっとシェアしたり、抱え込まないようにしたり。育児も仕事もチームでやるという概念を持つといいですよね。
津田:僕は男性だから、経沢さんの話に100%共感できる訳ではないのですけど……あえていうならば、テクノロジーの恩恵は受けられますよね。わかりやすいのは、全自動洗濯機や食器洗い機、ルンバを使ったり。「フェミテック」という単語に注目が集まっているのもその流れだと思います。
テクノロジーやキッズラインなどのITサービスを使って、自分が自分として何かをやれる時間を作っていく。物理的に解決可能なことをしてから「自分がどうするのか」を問うのが大事ですよね。
「子供をあずける罪悪感」とどう向き合う?
経沢:思考のアップデートが、必要だと思います。子どもを自分で育てていない罪悪感、みたいなものに多くの人がこだわりすぎてはいけないなと。
考え方としては、多くの大人に触れたほうが、子どもの視野が広がるし、教育的見地としても預けるのはいいことなんだとメリットの部分にも、思い直せればいいんじゃないかな。
津田:ファクトを出していくことも大事ですよね。「子どもはつきっきりで育てるよりもいろんな人に出会った方がいい」というのも、教育経済学者の中室牧子さんが『学力の経済学』という本で紹介しています。勤勉性や協調性、リーダーシップ、社交性などの「非認知能力」を鍛えた方が学歴や雇用、収入に好影響を与えると。
ベビーシッターや家事代行を使うのは、自分のためにも子どものためにもむしろ良い、ということを根性論や精神論じゃなく説得できる材料が出てきていますから。
経沢:お母さん自身、罪悪感があるから預けられない人、多いんです。だから、キッズラインで最初女子大生軍団を作って、シッターではなく家庭教師の「先生」が家に来ている、という風にしたら、人に言えるし利用できる、という流れもありました。
人の言うことを聞いても、幸せにはなれない
経沢:昔の話ですけど、私は就活で広告代理店志望でしたが、「代理店で女性は男性の2倍がんばっても評価されないよ」と言われて、残念な気持ちになりました。
特に私は女性だったので、自分の人生や幸せを追求した時に、イニシアチブを他人に握られすぎるリスクについて考えていました。
津田:結婚生活も似てますよね。旦那とは冷めきっていて、むしろ一緒にいるのもツライ状況。それでも、子どもがいるし、暮らしていけるかわからないから……と離婚できずに縛られたら地獄ですから。
経沢:自分の幸せをみんな、もっと考えていいと思うんです。子育てだけに縛られなくていい。もっと自分がどうしたいかを考えて、その先にみんなの幸せがある。
経験もなく想像もできない人にツラさを説明しても、絶対に届かない
経沢:津田さんはあいちトリエンナーレ2019の芸術監督をされて、「ジェンダーギャップ」はどうしたら変わると思いましたか?
津田:ジェンダーの問題は、個別の問題だけ見るとわからないんですよ。
経沢:一人一人の事情がありますもんね。
津田:そうなんです。想像力が及ばない人に言葉で説得しようとしても届かないんですよ。だから、強制的に決定権のある人が構造を変える。これを繰り返す。そうやって、中長期的にみんなの意識を変えていく方がいいんじゃないか、ということに思い至りました。
たとえばですけど、「きれいなお母さんが出てきて、洗濯物を干しているCM」があるとします。ずっと家事労働を押しつけられてきて「働きたいのに働けなかった!」という女性がそのCMを見ると、抑圧の象徴に見えてしまうんですね。
これって、単体では評価できなくて、累積的な経験の有無によって見方が変わってしまうんですよ。
だから僕は、構造とか制度を変えちゃう方が早いだろうと思いました。今回の「トリエンナーレ」のように、起用する男女を同数にしていけば、選ぶ側の意識も変わってきますから。
経沢:なるほど~! 津田さんは「あいちトリエンナーレ」の芸術監督をされたのは、活動範囲を広げたからですか?
津田:実は、依頼があったんです。2017年6月に「あなたはあいちトリエンナーレ2019の芸術監督に選ばれました」ってメールがきたんですよ!
「なんだか振込詐欺みたいだな」と思って(笑)。メールアドレスを確認したら、愛知県から送られてきていたので、「どうやら本物っぽいぞ」と。どうやって断ろうかなって最初は考えていてました。
経沢:最初は、断ろうと思ってたんですね。
津田:僕、アートと縁遠い生活をしていたので。ただ、これだけの大きなプロジェクトは一生に一度にあるかないかです。僕自身、東北の復興イベントを企画しましたし、アートとジャーナリズムって近い部分があると思っていたのでお引き受けしました。
活動してわかったことは、現代美術の世界でもM字カーブ問題があって、子どもを産んだことで戻ってこなくなっちゃう人が多いこと。そういう人たちに機会を与えて光を当てるのは重要なんですよね。
「あいちトリエンナーレ2019」で起用した女性作家で、妊娠中だったり、出産したばかりの方が結構いるんですよ。
さきほど、経沢さんがおっしゃったように、孤独になっている女性はなかなか仕事を見つけられない。けれども、横のつながりがある人は「あなたの能力があれば、週3でもこういう仕事があるよ」とか、情報がもらえますよね。
そうして少しづつ働くこともできるし、ワーキングプランを立てられるような「人との出会い」って大事。ロールモデルが重要なのは作家も同じです。
経沢:情報をシェアすることが、大事ですよね。
津田:「あいちトリエンナーレ2019」の多くの会場では、託児サービスがあって、そこで子どもが自分でアートをつくれるようにしたんです。しかも無料です(笑)! 親子でつくってもいいし、託児に預けて自分はじっくり何時間でもアート作品を楽しむ、ということもできます。
経沢:楽しそうですね。
津田:ジェンダーギャップの問題に取り組んだ「トリエンナーレ」ですが、親子連れでも楽しめる芸術祭にするのは、すごく意識したので、美術に興味がある人は来てもらいたいですね。
取材後記
これからの「子育て」について、新しいファクトに基づいた議論が交わされた今回の対談。これまで常識とされていた精神論や根性論から一歩アップデートし、「自分の幸せ」を起点に子育てやキャリアをデザインする、ということの重要性が語られました。