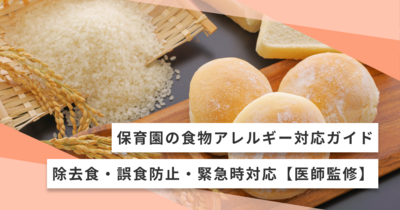保育園に入園すると、多くの園では慣らし保育が始まります。しかし、思ったよりも日数がかかるケースも少なくありません。「慣らし保育が終わらない理由」と、年齢ごとの期間の目安、スムーズに進めるための対処法について、現役保育士がわかりやすく解説します。
記事のポイント
⚫︎慣らし保育の期間は子どもの年齢や性格で異なる
⚫︎子どもの様子によって、慣らし保育期間は延びることがある
⚫︎入園前からサポート体制を整えておく
そもそも慣らし保育とは?必要な理由と期間の目安

慣らし保育とは何か
慣らし保育とは、子どもが保育園に通い始める際に実施される準備期間のことです。
最初は短い時間から始めて、少しずつ保育時間を延ばしていきます。段階を踏むことで、子どもが新しい環境に無理なく慣れていけるようにすることが目的です。子どもの情緒の安定を大切にしながら、保育園での生活へスムーズに移行するための大切な準備期間として、多くの園で取り入れられています。
慣らし保育の期間は、どれくらい?
慣らし保育の一般的な期間は、2〜3週間程度です。ただし、子どもの年齢や性格によって、慣れるまでにかかる時間には個人差があります。特に、初めて集団生活を経験する子どもは、慣れるまでに時間がかかるケースもあります。
一方で、保育園にすぐに慣れる子どももいます。また、保護者の就労状況に配慮して、「慣らし保育を行わない」「数日で終える」といった柔軟な対応をしている園もあります。
なお、
慣らし保育は法律で義務づけられているわけではないため、実施するかどうかや、その期間の長さについては、園と保護者が相談しながら決めていくのが一般的です。
0歳・1歳の慣らし保育の期間はどれくらい?

0歳から1歳にかけての子は、保護者と離れることが初めてであることが多いため、多くの子が慣らし保育を通して少しずつ園生活に慣れていきます。では、この時期の子どもには、どれくらいの期間が必要なのでしょうか。
0歳児の慣らし保育期間
0歳児の場合、
人見知りが始まる時期かによって、慣らし保育の期間が異なります。人見知りは7〜8ヶ月頃に始まりますが、その時期は子どもによって異なるので、あくまで目安として捉えておく程度にとどめましょう。
人見知りが始まる前であれば、保育園に預けても泣かないことが多く、「慣らし保育をしなくても大丈夫なのではないか」と思うかもしれません。しかし、家庭とは異なる匂いや音の中で生活するので、赤ちゃんなりにストレスを感じている場合があります。
泣かないから平気だと思わず、1〜2週間ほどかけて保育園の環境に慣れていくプロセスをたどることが、子どもには必要です。
人見知りが始まった後の場合は、不安を感じて、時に激しく泣いてしまうかもしれません。その場合、2週間〜1ヶ月ほどを慣らし保育期間として見込んでおくとよいでしょう。子どもによっては、1週間ほど大泣きした後、急に泣かずに登園できるようになるケースもあります。
慣れるまでの期間は子どもによって大きく異なるため、余裕を持った復職スケジュールを立てることをおすすめします。
1歳児の慣らし保育期間
1歳児は、人見知りや場所見知りが強く出る時期のため、保育園の環境に慣れるまでに時間がかかることがよくあります。個人差はありますが、
おおむね2週間から1ヶ月ほどの慣らし期間を想定しておくと、心に余裕を持ちやすくなります。慣らし保育を通じて、不安を感じたときに受け止めてくれる保育士との信頼関係が築かれ、さらに「楽しい」と感じられる遊びと出会うことで、子どもは保育園生活に慣れていきます。
1歳児の場合、はじめの1〜2日は遊ぶことに夢中になって、泣かずに過ごす子どももいます。「慣らし保育をしなくても大丈夫かな?」と感じるかもしれませんが、突然自分の置かれている状況に気がついて泣き出すケースもあるため、慎重に慣らし保育を進めます。
ベビーシッターを探してみる
2歳、3歳以上の慣らし保育はどうなる?

2歳や3歳以上の子どもの場合には、慣らし保育にどのくらいの期間が必要なのかを見ていきましょう。
2歳児の慣らし保育期間
2歳児は、いわゆる「イヤイヤ期」と呼ばれる時期にあたり、
自己主張が強くなるのが特徴です。そのような時期に、見知らぬ環境で集団生活を始めることには、強い不安や抵抗を感じるのは自然な反応です。そのため、
慣らし保育には2〜3週間ほどかかると想定しておくと安心です。
少しずつ保育園の環境に慣れてくると、子どもにも周囲を見る余裕が生まれます。他の子が遊んでいるおもちゃに興味を持ったり、おやつや給食を食べてみたいと感じたりするようになり、園での生活にも次第に溶け込んでいけるでしょう。
3歳以上児の慣らし保育期間
3歳以上の子どもについては、これまでに
集団生活を経験したかどうかによって、慣らし保育に必要な期間が変わります。 たとえば、3歳から初めて保育園に通う場合は、保護者と離れることに強い不安を感じやすく、園の生活に慣れるまでに時間がかかる傾向があります。個人差はありますが、一般的には
2〜4週間程度の慣らし保育が必要 になることが多いでしょう。
一方で、小規模保育園や保育ママ、他の保育園などで集団生活に慣れている子どもが転園してくる場合は、慣らし保育を行わずに通常保育に入るケースもあります。ただし、子どもの様子によっては、1〜2週間ほどの慣らし保育が必要になることもあるため、無理のないペースで進めていくことが大切です。
慣らし保育が終わらない?!その理由とは

実は子どもの様子によっては、予定していたよりも慣らし保育が長引くことがあります。慣らし保育が予定通り終わらないことがあることを念頭に、保護者は仕事の復帰時期を検討しておく必要があります。なぜ慣らし保育が長引くことがあるのでしょうか?その主な理由について、見ていきましょう。
理由1:分離不安が強く、ずっと泣いている
これまでずっと保護者と過ごしてきた子どもにとって、急に離れて過ごすことは大きな不安や恐怖を伴います。
特に幼い子どもは、「親が目の前からいなくなった=もう会えないかもしれない」と感じてしまう こともあり、不安で泣き続けることがあります。これを「分離不安」と呼び、成長の過程で多くの子どもに見られる自然な反応です。
登園時に泣いていても、日中の保育時間に少しずつ機嫌よく遊べるようになっていけば、慣らし保育は順調に進んでいると判断できます。一方で、登園からお迎えまでずっと激しく泣いているような場合は、子どもへの心身の負担を考慮して、短時間での保育を継続するなど、慣らし保育の期間が延びる可能性があります。
理由2:保護者の不安が子どもに伝わっている
子どもは、保護者の気持ちをとても敏感に感じ取ります。「本当に預けて大丈夫かな」「泣いているのに置いていくのはかわいそう」といった
不安や罪悪感を親が抱いていると、無意識のうちに親の表情や態度に現れ、子どもに伝わってしまいます。
保育園に対して信頼を持てなかったり、自分自身の気持ちが整理できていなかったりすると、子どもも不安を感じやすくなり、なかなか園に慣れない原因になります。何気ないひと言や表情、ふとした仕草も、子どもにとっては大きなサインです。
保護者が安心した気持ちで登園を見守ることが、子どもにとっても安心につながります。
理由3:保育園で飲食ができない
家庭では問題なく食事ができる子どもでも、
環境の変化によるストレスや不安から、保育園では飲食を拒むことがあります。特に乳児の場合、ミルクを飲まなかったり、離乳食を口にしなかったりする状況が続くと、栄養や水分が十分に補給できず、健康へ悪影響を及ぼします。そのため、保育園では子どもが少しでも飲食できるようになるまで、慣らし保育の期間を延ばして対応することがよくあります。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
慣らし保育が長引くことの影響

慣らし保育が予定よりも長引くと、家庭生活にも仕事にも影響が出てきます。慣らし保育が長期化することで起こりうる主な問題について見ていきましょう。
生活リズムが整いづらい
慣らし保育の期間中は、保育時間が短く、降園時間も日によって異なることが多いため、子どもの生活リズムが安定しづらくなります。
食事やお昼寝の時間が毎日変わると子どもが混乱し、情緒が不安定になってしまいます。
影響を受けるのは、子どもだけではありません。先の見えないスケジュールに保護者もストレスを感じやすくなります。日々の見通しが立てづらい状況は、大人にとっても大きな負担になりかねません。
予定通りに復職できない可能性がある
多くの保護者は、職場復帰の時期に合わせて慣らし保育のスケジュールを立てています。ところが、子どもが思ったよりも園に慣れるのに時間がかかり、予定していた復職日までに慣らし保育が終わらないケースもあります。
「子どもに無理をさせたくないけれど、仕事には戻らなければならない」という板挟みの状況は、保護者にとって大きなストレスになります。
仕事の調整が難しくなる
慣らし保育の期間中に働き続ける場合、保護者は休みを取ったり、早退をしたりする必要が出てきます。職場によっては上司の理解を得られなかったり、同僚の業務負担が増えてしまったりと、職場での居心地が悪くなってしまうかもしれません。子育てに理解のある会社に勤務していたとしても、休みや早退が重なると、周囲に後ろめたさを感じる方も少なくありません。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
慣らし保育をスムーズに進めるためのコツ

慣らし保育は、子どもが安心して園生活をスタートさせるための大切な時間です。保護者が適切に関わることで、子どもの不安を和らげ、少しずつ園に慣れていけるようになります。慣らし保育をよりスムーズに進めるための具体的なポイントをご紹介します。
保育園の利用を前向きに捉える
子どもを保育園に預けることに、不安や罪悪感を抱く保護者は少なくありません。しかし、保育園は「子どもを預ける場所」だけでなく、人との関わりの中で生きる力を育む「学びの場」でもあります。
「子どもが成長していく場所」として保育園を捉えることで、前向きな気持ちで保育園生活をスタートできるのではないでしょうか。
保育園では、保育士に子育ての相談ができたり、子どもの成長を一緒に喜んだりする機会があります。また、園の行事などを通じて、子育ての悩みを共有できる保護者と出会うこともできます。保育園に通うことで「子育ての仲間」が増え、たくさんの人に支えられながら子育てができることは、保育園を利用するメリットのひとつです。
預けるときに、明るい言葉をかける
保育園に子どもを預けるときは、
短くて明るい言葉を使うのが効果的です。たとえば、「今日も楽しんでね」「○時にお迎えに来るよ」といった言葉を笑顔で伝えることで、子どもは安心します。反対に、いつまでも別れを引き延ばしてしまうと、子どもの中で不安な気持ちが膨らんでしまいます。
帰宅後には「今日はどんなことが楽しかった?」と聞いてみましょう。1日を前向きに振り返ることができます。
前向きな会話で1日を終えることで、「明日も保育園に行きたい」という気持ちにつながりやすくなります。
保育士とコミュニケーションをとる
日々の送迎の際には、子どもの家庭での様子や気になることを簡潔に伝え、保育園での様子についても積極的に保育士へ聞いてみましょう。
話すのが得意でない方は、連絡帳を活用するとよいでしょう。
不安や心配がある場合は、個別面談の機会をお願いするのはいかがでしょうか。子どもがいない場所で、ゆっくりと話をすることができ、気持ちを整理しやすくなります。実は保育士も、保護者とどのような距離感で接すればよいか、初めは戸惑うものです。安心して園生活を送るためにも、遠慮せずに声をかけてみてください。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
慣らし保育が終わらないときには、ベビーシッターへの依頼を検討しよう

どれだけ対策をしても、子どもによっては新しい環境に慣れるのに時間がかかり、慣らし保育が予定よりも長引いてしまうことがあります。そんなときは、ベビーシッターを頼るという選択肢もあります。たとえば、復職日が迫っているにもかかわらず慣らし保育が終わらない場合や、復職後も早退が続いてしまうような状況では、
ベビーシッターに依頼することで、子どものペースに合わせて慣らし保育を進めやすくなります。
また、慣らし保育が終わった後でも、保育園のお迎えに間に合わないときや、体調不良で登園できない日などにもベビーシッターが活躍します。働きながら子育てをする上で、非常に心強い存在です。保育園生活は、慣れるまでに時間がかかることもあります。
入園前から信頼できるサポートを確保しておくことで、子どもも保護者も安心して新しい生活をスタートできます。
キッズラインならスマホからシッターを探せる
ベビーシッター・家事代行サービスを運営する「キッズライン」なら、パソコンやスマホで簡単に
ベビーシッターを見つけることができます。「慣らし保育が終わらないまま復職日が近づいている」といった状況では、勤務スケジュールに応じて柔軟に対応できるベビーシッターは、保護者の助けになります。通園の補助や短時間のサポートを通じて、子どもは安心できる環境の中で少しずつ園生活に慣れていくことができます。
保護者も安心して仕事に戻れるため、
復職と子育ての両立をスムーズに進めるうえで心強い支えとなるでしょう。保育園での勤務経験を持つシッターも多く、保護者の気持ちを理解しながら、きめ細やかにサポートしてくれる点も安心です。復職を控えた保護者にとっては、スケジュールに合わせた柔軟なサポートが受けられることも大きなメリットです。
勤務初日や復職直後の短時間サポートなど、必要に応じて活用できます。保育園とベビーシッターをうまく併用することで、無理のないペースで慣らし保育を進められるのは大きなメリットです。子どものリズムに合わせた柔軟な対応ができるのも、ベビーシッターならではの魅力と言えるでしょう。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
■保育士ライター 佐野希子
18年目の現役保育士。独学で認定試験に合格し、幼稚園教諭の資格も取得。他に社会福祉士の資格も保有。現在は副主任として保育現場の指導とサポートに努めている。
▼あわせて読みたい
慣らし保育はいつから?基本的なスケジュールと上手な進め方【保育士監修】
看護休暇は無給!? 2025年4月の法改正で対象年齢や取得条件はどう変わる?
ベビーベッドはいつまで使える?卒業の時期と寝かしつけ方法
▼記事一覧に戻る
KIDSLINE編集記事一覧
▼TOPページに戻る
KIDSLINE TOPページ