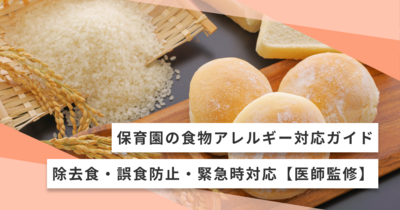「仕事が休みの日も、保育園に預けていいのか」と迷った経験はありませんか?仕事がお休みの日に保育園を利用することに、罪悪感を覚える保護者は少なくありません。保育園利用のルールやマナー、子どもの気持ちへの配慮など、現役保育士がわかりやすく解説します。
記事のポイント
⚫︎仕事が休みの日の保育園利用は問題ないが、運用は園によって異なる
⚫︎親が自分の時間を確保できるのはメリット
⚫︎お迎えの時間を早めることで、子どもの気持ちに配慮しよう
仕事が休みの日でも保育園を利用できる?
 仕事が休みの日に子どもを保育園へ預けても、法的には問題ありません。
仕事が休みの日に子どもを保育園へ預けても、法的には問題ありません。ただし、実際の運用は、保育園によって異なります。たとえば、休日の利用に制限を設けている園もあれば、理由を問わず利用を受け入れている園もあります。見学や入園説明会の際には、次の点を確認するとよいでしょう。
・親の休日に子どもを預けられるか
・どのような理由であれば預かってもらえるか
・保育園に預ける際に、事前連絡が必要か
これらを事前に確認をしておけば、「休みの日に預けられると思っていたのに困る」といった事態を防ぐことができます。
筆者が勤務している保育園では、保護者が仕事を休んでいる日でも子どもを預けることができます。子どもの負担を考慮し、
午前9時から午後4時までの預かりを提案していますが、基本的には保護者の希望に沿って対応しています。
近年、
保育園の役割は「子どもを預かる」だけでなく、「保護者を支援する場」であるという意識が広まりつつあります。 そのため、仕事が休みの日にも利用できる保育園は、今後ますます増えていくかもしれません。
仕事が休みの日の保育園利用、どう判断する?

「仕事が休みの日でも、子どもを保育園に預けていいのか」と考える保護者は少なくありません。中には「休みなのに預けるのは少し気が引ける」と感じる人もいれば、「自分の時間を確保したい」「リフレッシュのために預けたい」と積極的に利用を検討する人もいます。
家庭の状況や考え方はさまざまだからこそ、
親と子ども双方の視点から、保育園を利用するかを見直してみることが大切です。ここでは、休日の保育園利用を判断する際に押さえておきたいポイントをご紹介します。
親のひとり時間の確保
仕事が休みの日に保育園を利用する最大のメリットは、
保護者が自分の時間を確保できることです。
働く親は、普段の生活で仕事と子育てに追われ、なかなか自分の時間を持てないものです。心身ともに疲れがたまりやすく、気づかないうちにストレスが蓄積してしまいます。
こうした中、仕事が休みの日にリフレッシュの時間を取ることはとても大切です。気持ちに余裕が生まれ、より穏やかに子どもと接することができるからです。
日々の忙しさの中では、どうしても家事まで手が回りません。休日に子どもを預けることで、
掃除や洗濯、買い物などをまとめて行う時間が持てます。「家事をやらなければ」という気持ちに追われる状態から解放されると、生活にリズムが生まれ、心にも余裕ができます。
さらに、趣味や学びの時間を持つことも大切です。「親」としてだけでなく、「一人の人間」としての充実感を得ることができ、結果として心のゆとりにもつながります。
自分の時間を持つことは、決してわがままではありません。むしろ、親が健やかでいることが、結果的に子どもにも良い影響をもたらします。保育園を利用することは、悪いことではなく、前向きな選択なのです。
子どもの気持ちへの配慮
仕事が休みの日に保育園を利用する際は、
子どもの気持ちにしっかり寄り添いましょう。
「どうしてママやパパはお休みなのに、自分だけ保育園に行くの?」と疑問を抱く子どもも少なくありません。「ママやパパと一緒に過ごしたい」と思っているかもしれないからこそ、保育園に預けられることで不安や寂しさが湧き、情緒が不安定になることもあります。登園前には、子どもの年齢や理解度に合わせて、わかりやすく理由を説明してあげましょう。
また、
お迎え時間をいつもより早めに設定することで、子どもが納得しやすくなるケースもあります。「早迎え」は、子どもにとって特別でうれしい体験になることが多いからです。親のリフレッシュはとても大切ですが、子どもの気持ちを置き去りにしないようにしながら、家庭に合った保育園の利用方法を考えていきたいですね。
利用頻度と目的の見直し
定期的に平日休みがある方は、保育園を利用する頻度や目的を時々見直してみましょう。毎回のように「なんとなく」で預けるのではなく、「本当に必要な日」を選んで利用するのがおすすめです。
たとえば、集中して家事を片付けたい日、体調が優れずゆっくり休みたい日、大切な予定がある日など、
具体的な目的があると、子どもにも納得してもらいやすくなります。
また、1か月単位でスケジュールを振り返り、「今月はどの日に保育園を利用するか」をあらかじめ決めておくと、無理のない計画が立てやすくなります。親のための時間と、子どもと過ごす時間。そのどちらも大切にすることが、バランスのとれた暮らしにつながっていきます。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
仕事が休みの日の保育園利用で気を付けること

仕事が休みの日に保育園を利用することに、
後ろめたい気持ちを抱く必要はありません。ただし、子どもを預ける際には、いくつか意識しておきたいポイントがあります。ここでは、休日に保育園を利用する際に、親が特に気をつけたいことをわかりやすく紹介します。
事前に園のルールを確認する
保育園によって、仕事が休みの日の登園をどう扱うかの方針は異なります。まずは、お子さんが通っている
園のルールをしっかり確認しましょう。
入園説明会や入園式で配布された資料に記載があることもありますが、内容が曖昧だったり、書かれていない場合もあります。そのときは、遠慮せず園に直接確認するのがおすすめです。
また、休日の登園が認められている園でも、
「事前に休日であることを伝えてほしい」「当日の連絡先を知らせてほしい」など、細かなルールやお願いごとがある場合も少なくありません。
あらかじめ園の方針を把握しておくことで、トラブルを防ぎ、安心して子どもを預けることができます。
利用時間に配慮する
休日に保育園を利用する際は、子どもへの負担を考えて、預ける時間を必要最小限にとどめるとよいでしょう。開園から閉園まで預けるのではなく、
用事が済んだらできるだけ早めにお迎えに行くよう心がけましょう。
多くの子どもは「ママやパパと一緒にいたい」と思っています。必要なことだけを済ませて早めに迎えに行けば、子どもの不安や寂しさを和らげることができます。
とはいえ、中には「もっと保育園で遊びたかった!」と、早めのお迎えを嫌がる子もいます。子どもの反応は年齢や性格によってさまざまです。
子どもの様子を見ながら、保育士とも相談して、無理のない登園スケジュールを一緒に考えていけるとよいですね。
子どもとの時間も大切にする
子どもが「ママやパパと一緒にいたい」と思ってくれる期間は、意外に短いものです。今は忙しさの中で「一人の時間がほしい」と感じている方も多いかもしれませんが、意識して子どもと過ごす時間も大切にしましょう。
たとえば、午前中は保育園に預けて家事や用事を済ませ、午後は親子で公園に出かけるなど、
オンとオフにメリハリをつけたスケジュールを組むのもおすすめです。子どもの話にしっかり耳を傾けたり、スキンシップを取ったりする時間は、親子の絆を深めてくれます。
また、子どもは「親が休みなのに、なぜ自分は保育園に行くのか」が分からないこともあります。そんなときは、「今日はママ(パパ)の用事が終わったら、一緒に○○しようね」など、前向きな声かけをしてあげましょう。納得して登園できる気持ちの準備につながります。
仕事が休みの日に保育園に預ける際のマナーと注意点

保育園は、子どもたちが安心して過ごせる環境を整える責任を担っています。そのため、保護者が保育園を利用する際は、
園のルールをしっかり守ることが大切です。仕事が休みの日に保育園を利用する場合に、保護者が気をつけたいマナーや注意点について、わかりやすく解説します。
理由と連絡先を伝える
仕事が休みの日に保育園を利用する際は、
理由を正直に伝えることが大切です。何も伝えなければ、園側は通常通り仕事に行っているものと判断してしまうかもしれません。
保育園にとって重要なのは、子どもの様子に応じて、保護者とすぐに連携が取れることです。たとえば、緊急で連絡が必要な場合でも、どこに電話をすればいいのか分からなければ、対応が遅れてしまう可能性があります。
最近では、
保護者のリフレッシュや家事の時間確保の必要性を理解してくれる保育園も増えています。罪悪感を持つ必要はありません。「今日は家事をまとめて行いたいので、何かあれば自宅にご連絡ください」といった形で、利用の目的と連絡先をしっかり伝えておくようにしましょう。
お迎えの時間を守る
仕事の有無にかかわらず、お迎えの時間は守ってください。特に、仕事が休みの日には「時間に余裕があるから大丈夫」と油断しやすいため、
普段よりも時間を意識しましょう。
保育園では、子どもの人数に応じて保育士の配置を調整しています。お迎えが遅れると、保育士の勤務時間やその後の保育スケジュールに影響が出るだけでなく、子ども自身も不安になってしまうかもしれません。「まだ大丈夫かな」と思っているうちに時間が過ぎてしまうことのないよう、ゆとりを持った行動を心がけましょう。
子どもの体調に配慮する
仕事が休みの日に保育園を利用する場合は、特に子どもの体調に注意を払いましょう。少しでも体調がすぐれない様子が見られたら、無理に登園させず、自宅でゆっくり休ませることが大切です。
平日は仕事の都合で預けざるを得ないこともありますが、仕事が休みの日であれば家で看病する時間を取りやすいはずです。「熱がないから大丈夫」と判断せず、
子どもの表情や機嫌、食欲などを含め、総合的に様子を見て登園を決めましょう。体調が万全でないまま集団生活に入ると、他の病気にかかってしまう可能性もあります。子どもの健康を最優先に考え、無理のない登園を心がけるようにしましょう。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
保育園以外にもある!親の仕事が休みの日の子どもの預け先

子育てを続けるうえで、まわりのサポートは欠かせません。保育園が利用できない日や、利用にためらいがあるときのために、
保育園以外の預け先もあらかじめ検討しておくと安心です。保育園以外の子どもの預け先として考えられる選択肢をご紹介します。
祖父母やきょうだいなどの親族
祖父母やきょうだいなどの親族が近くに住んでいる場合は、必要なときに頼りやすく、子育てを支えてくれる存在として非常に心強い存在になりえます。子どもにとっても、
普段から顔を合わせている親族は親しみがあり、リラックスして過ごせます。
一方で、「気をつかってしまうため、預けにくい」と感じる保護者もおり、子どもを預かってくれる人が見つからない場合の最終手段として考える人も少なくありません。預かる側も仕事や家庭の事情を抱えていることが多く、頼る側としても遠慮や心理的な負担を感じやすいものです。
そのため、
無理のない範囲で協力をお願いすることが大切です。感謝の気持ちを忘れず、関係性に配慮しながら、双方にとって心地よい形での支援体制を築くことが、長く頼れる関係づくりにつながります。
ファミリーサポートセンター
ファミリーサポートセンターは自治体が運営している、子育て支援制度です。地域の中で子育てを助け合う仕組みで、子どもを預かる側の「提供会員」と、預けたい側の「依頼会員」が登録し、間に立つコーディネーターが調整を行います。
料金が比較的安価なのが大きな魅力で、保育園よりも柔軟な時間帯に預かってもらえることも多くあります。近所の提供会員の自宅で預かってもらうため、アットホームな雰囲気の中で過ごせる点も特徴です。
ただし、希望する日時に必ず預かってもらえるとは限らないので、早めに依頼をしましょう。また、
事前に提供会員と顔合わせを行い、子どもが安心して過ごせる相手かどうかを確認しましょう。
ベビーシッター
ベビーシッターサービスとは、育児経験のある人や、各事業者の基準を満たしたベビーシッターが、利用者の自宅で子どもを預かってくれる仕組みです。
保育園や祖父母に頼れない突発的な事情にも対応できる柔軟性があり、希望する時間帯や曜日を指定しやすい点が特徴です。
基本的に自宅で保育が行われるため、子どもは慣れた環境で安心して過ごせます。また、送り迎えの手間がなく、保護者は自分の時間をより有効に使うことができるのも大きなメリットです。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
ベビーシッターの活用で、柔軟な子育てを実現しよう

仕事が休みの日に子どもを預けて自分の時間を持つことは、結果的に子どもにも良い影響を与えます。保育園が利用できる場合は、子どもとの時間も大切にしながら、無理のない範囲で活用していきましょう。
ただ、「保育園に預けてもいいのかな」「家族に負担をかけてしまっていないか」と心配になることもありますよね。そんなときには、
ベビーシッターサービスへの依頼も一つの方法です。
保育士資格を持つプロや、研修を受けたシッターが自宅で保育をしてくれるため、子どもは慣れた環境で安心して過ごすことができます。また、子ども一人ひとりのペースや好みに合わせた保育ができるのも、ベビーシッターの大きな魅力です。
自分の時間を確保しながら、子どもにはきめ細やかなケアを届けられる。そんな
バランスの取れた子育てをサポートしてくれる手段として、ベビーシッターの活用を検討してみてはいかがでしょうか。
キッズラインならスマホからシッターを探せる
ベビーシッターのマッチングプラットフォームであるキッズラインは全国47都道府県にベビーシッターがおり、スマホから24時間いつでも検索・依頼をすることができます。ベビーシッターは、保育士資格など8つの資格または研修修了者のみが登録可能で、保育のプロが揃っています。
保護者がしっかりと休み、自分の時間を持つことで、子どもにも穏やかな気持ちで接することができ、子どもにとってもメリットがあります。保育園の利用をためらうときのほか、送り迎えの手間を省きたいときなどには、ベビーシッターへの依頼がおすすめです。
キッズラインでベビーシッターを依頼するには、事前に顔合わせまたは事前面談が必要です。急に依頼する必要がある場合に備えて、まずは一度お試しで頼んでみるとよいでしょう。
子育ての疲れを一人で抱え込まず、時にはサポートを得ながら子どもと向き合っていきたいですね。
今すぐベビーシッターを依頼してみる
■保育士ライター 佐野希子
18年目の現役保育士。独学で認定試験に合格し、幼稚園教諭の資格も取得。他に社会福祉士の資格も保有。現在は副主任として保育現場の指導とサポートに努めている。
▼あわせて読みたい
看護休暇は無給!? 2025年4月の法改正で対象年齢や取得条件はどう変わる?
親が体調不良の時、保育園に預けてもよい?現役保育士が教える注意点
慣らし保育はいつから?基本的なスケジュールと上手な進め方【保育士監修】
▼記事一覧に戻る
KIDSLINE編集記事一覧
▼TOPページに戻る
KIDSLINE TOPページ