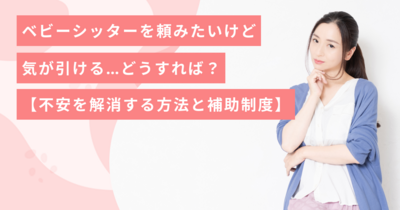おもちゃや衣類、本、学習プリントなど、年々子どものものが増えることから整理収納にお困りのご家庭もあるのではないでしょうか?収拾がつかなくなり、片付けてもすぐに散らかるということを繰り返してしまうのが、子ども用品ですよね。理想的なのは、子ども自身が自分のモノを片付けられるようになることです。そこで今回は、子どもが自分で片付け、整理収納ができるようになるヒントをご紹介します!
子どもが整理・収納できるようになるメリット
はじめに、子どもが自分で整理収納できるようになるメリットについてお伝えします。子ども自身が片付けから得られる「生きる力」を学校教育でも推奨しています。
きれいに整理・整頓する日本の文化に海外からも絶賛
小学校の学習指導要領では「住まいの整理・整頓や清掃の仕方を考え、快適な住まい方を工夫する」とし、自分たちの通う学校をきれいに掃除することは「生きる力」を身につけることとして目標を掲げています(※1)。
日本では公立の小中学校に通う子どもたちは、給食後や放課後に掃除するのは当たり前の光景ですがが、欧米など海外の学校清掃は、清掃員がやるのが当たり前です。そのため日本の子どもたちの掃除風景がテレビなどで紹介されると「すばらしい!」と絶賛されるのです。
※1) 小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説 家庭編
※参照) 学校清掃と生徒指導─ 「福井掃除に学ぶ会」の調査から ─
掃除や整理・整頓が子どもにもたらす7つの教育効果
片付けが身に付くと、様々な力が培われると言われています。どのような教育効果があるのか、そのメリットをみていきましょう。
① 判断力・先を見通す能力
整理・整頓は、自分で「モノが必要か、必要ではないか」を選別することになります。選別することによって、判断する力も養われていきます。この作業は、この先何が必要で何が不要になるのか、といった先を見通す能力を養うことにも繋がるのです。また、モノを整理・整頓することによって、頭の中の整理ややるべきことの優先順位の整理を付けられるようにもなります。
② 創意工夫する力
整理・整頓をするためには、「何を」「どこに」「どのように片付けるか」といった工夫が必要です。その工夫ができるようになることで「考える力」が養われます。また、整理・整頓を通じて「自分が管理できる量」を体験的に知ることができます。それによって「足るを知る」ということを学びます。自分が何を持っているかを把握できれば、必要以上に物を欲しがらなくなるのです。
③ 責任感・自立心・自主性が生まれる
子ども達は「自分で遊んだおもちゃは自分で片付けましょう」と教えられてきたことでしょう。「自分のモノは自分で片付ける習慣」によって、責任感・自立心・自主性が養われるため、ご家庭内だけでなく集団生活でも声がけがされるのです。
④ 集中力が高まり、成績が上がる
片付いたきれいな部屋は落ち着いた環境です。そのような環境は、子どもの集中力を高めることにもつながります。何がどこにあるか一目瞭然であれば、効率よく学習ができるため成績が自然に上がるとも言われています。
⑤ 空間の使い方と空間把握力を学ぶ
整理・整頓するには、物の大きさを捉える必要があり、空間把握の訓練に繋がります。自分のスペースを整理・整頓することで、「空間」をより効率よく使えるようになります。作業効率が上がるのはもちろんのこと、きれいな状態を保つ努力を自分自身がすることで、子どものやる気と心の成長を促します。
⑥ 感謝の気持ち・思いやりの気持ちを育てる
実際は、子どもが自分のモノを整理・整頓して、きれいに保つことは容易なことではありません。この大変さは、毎日部屋を片付けてくれるママやパパが一番理解されていることでしょう。きれいな状態を保つためには、手間と労力がかかります。そのことを子どもが理解することで、他人への感謝の気持ちを育むことができます。
⑦ 時間的・SDGs的・精神的な効果が得られる
整理・整頓ができるようになると、探し物が減り時間の無駄がなくなります。何度も同じものを買ってしまうといった無駄もなくなりますし、環境への負荷も減らすことにもつながります。また、きれいに整理・整頓された空間は精神的な安定をもたらすため、自己管理にも効果的です。
子どもが整理・整頓できるようになるコツ【方法】

「整理・整頓は、とても面倒なこと」と思っていないでしょうか?前提として、片付けは面倒なことではなく、「とても気持ちいい作業!」という感情を育てることが大切です。
子どもが片付けられない原因と解決法
整理・整頓に対する前向きな感情を育てるために、子どもが面倒くさがらずに済む「片付けしやすい仕組み」を作ってあげましょう。そこで、はじめに子どもが自分のモノを片付けられない原因と、それらの解決法をご紹介します。
【子どもが片付けられない原因と解決法】
・モノが多すぎる → 子どもが自分で管理・整理できる量にする
・モノの定位置が決まっていない → モノの住所を決める
・収納する場所がそもそも少ない → 子ども専用の収納場所をきちんと確保する
・種類ごとに細かく分類しすぎる → 大雑把な分類でOKとする
・片付けがワンアクションでできない → 使ったモノをすぐに整理できる場所に収納を作る
子どもが片付けしやすい環境づくり5ポイント
POINT① モノの「定位置」を決める
定位置が決まっていないと、片付けをするたびに「どこにしまおう?」と考えなければなりません。ですが、一度決めてしまえば、次からはしまう場所を考えなくても良いので片付けしやすくなります。 定位置を決めるときは、子どもと一緒に話し合いながら決めることで、子どもの自主性を尊重し、子供の目線にあった動線で片付けができます。
POINT② ざっくりと「大雑把な収納」をする
収納は完璧を目指すと親も子どもも長続きしません。「必要なモノを子どもが自分で見つけられる&片付けられる」と大雑把にとらえましょう。もし 決めた収納場所がいっぱいになったら、不要な物は処分するようにして、その時に最もよく使うものを優先しましょう。
POINT③ ひと目で全体が見渡せる「見える収納」
子どもの特性にもよりますが、子どもは大人より「視覚」でモノを記憶すると言われています。つまり、子どもが片付けしやすい収納とは「どこに何が入っているのかが一目で分かる収納」です。オープン棚や絵本の表紙が見えるラック、中身が見えるカゴなどがオススメです。
POINT④ 「子供の成長に合った収納アイテム」を用意する
小さい頃は、自分で片付けができる背の低い収納にしましょう。幼少期になったら、サイズや組み合わせが自由にできるカラーボックスなどもオススメです。収納ボックスは、一人で運べるサイズ・重さであることも重要です。
POINT⑤ 一時置き場の「とりあえず収納」をつくる
いつでもその都度、きちんと片付けするのは大人でも難しいものです。少しハードルを下げ、一時的に置いておく「とりあえず収納」を作ってみましょう。いっぱいになったら、または一週間に1回などルールを決めて親子で一緒に整理整頓していきましょう。
年齢ごとの整理・収納のコツ
整理・収納の仕方や方法論は、年齢によっても異なります。3歳から小学校高学年までを3つのグループに分けて整理・収納のコツをまとめました。
●3歳~5歳:ざっくり収納!
自分一人ではまだ整理・整頓は難しいので、「ざっくり分類」「ざっくり収納」がオススメです。この時期は「自分でできた!」という自信を持てることが何より大切です。大きめのバスケットなどに「入れるだけの収納」であれば、小さい子どもでも簡単に片付けができます。
●小学校・低学年:自分で身支度できる収納!
小学校入学後すぐは、自分で身支度するのは難しいものです。学校で使う物を1箇所にまとめて収納スペースを作りましょう。ランドセル、手提げカバン、教科書、ノートなど、ひと目で見渡せる収納法にすることで、1人で支度をしても忘れ物を防げます。
●小学校・中高学年:子どもの行動パターンに合わせた収納!
学習塾やサッカー、ピアノ、バレエ、英会話など、習い事が増えるのもこの時期です。子どもの生活パターン、行動パターンに合わせた動線で収納をしましょう。この年代の子どもには、自由に収納スタイルが変えられるカラーボックスを使った収納がオススメです。
子どもが整理整頓できるようになるコツ【声がけ】

子どもに自ら行動してもらう声がけのヒントをお伝えします。ポイントは「片付けなさい」と叱らないこと。叱られるのが嫌だから片付ける、という流れになると自主性が育まれません。
子どもが自発的に片付けしたくなる声がけ
叱られたら誰でもやる気をなくすものです。「ものすごく散らかしたね、すごい!」と驚き、「じゃあ片付けできるかな?」と自尊心をくすぐってみましょう。
【子どもがやる気になる声がけ】
・「どっちがたくさん箱にしまえるか競争しよう」など、片付けを楽しい遊びにする
・「床に何か落ちていないか、パトロールをお願いします」と任務を与え責任感を育てる
・「すごい!きれいに片付いたね」と驚き、達成感を感じさせる
・「どうやってこんなにきれいに片付けたの?ママにも教えて」と自尊心をくすぐる
・「片付けしてくれてママは助かったよ、ありがとう」と自己肯定感を高める
このように子供をその気にさせながら、できたらたくさん褒めてあげましょう。「片付けは楽しいもの」「整理・整頓は気持ちがいいもの」という気持ちを育てることが何より大事です。自分で片付けできるようになるまで、根気強く、一緒に楽しみながら声がけしていきたいですね。
子どもの整理整頓のやる気スイッチを入れるコツ
片づけは「今やっていることに区切りをつける」という意味もあります。そして、片づけができることによって「次の行動に切り替える練習」にも繋がります。そのため片付けのやる気スイッチが入ると、次の行動(ご飯・お風呂・宿題など)にもスイッチが入りやすくなります。はじめはうまくいかなくても「片付け→次の行動」を繰り返すことで習慣化されるでしょう。
やる気スイッチを入れる仕組みづくり
子どもは「できた!」「きれいになった!」を実感すると、達成感を感じて「次はこうしたらどうかな」など、創意工夫するようになります。子どものやる気にスイッチが入る仕組みづくりを4つご紹介します。
① 片付けタイムを作って習慣化
テーブルや床が散らかったままではご飯の準備が進められません。次の行動へ移るタイミングとして「片付け」を習慣化しましょう。夕食前に片付け、お風呂前に片付け、就寝前に片付けなど、毎日の生活習慣に 「片付けタイム」を設けていけば、自然と習慣化できるでしょう。
② 片付けの指示は具体的に
片付けが上手にできるようになるまでは、具体的な指示をした方が良いでしょう。例えば、「本は2段目の棚に戻してね」「おもちゃは黄色いおもちゃボックスに入れてね」などです。ただ「片付けなさい」と言うだけでは、抽象的すぎてどこに片付けるか迷ってしまいます。
③ 片付けができたら、その成果を褒める
しっかり片付けができたら、その成果を「具体的に褒める」ことが大切です。子どもの自己肯定感を育むためにも「褒めて伸ばす」というやり方がオススメです。例えば、「本を正しい向きで並べることが上手になったね」「ご飯前におもちゃがきれいに片付いて偉いね」などです。
このように具体的に言葉にすると、何が良かったのかを理解し、自信につながります。また、家族の一員として「みんなの役に立っている」という実感が得られることも大事なことです。
④ できない時は手伝ってあげてもOK
「夕飯前に片付けをする約束でしょ。やりなさい!」と叱るのではなく、子どもの様子を見て状況を認めてあげることも大切です。「今日はたくさん遊んだから疲れたよね。じゃあ、今日はママも手伝おうか?」と手を差し伸べる日があっても良いでしょう。
そうすることで、片付けのプレッシャーから解放されるだけでなく、「ママは自分のことをわかってくれている」という自己肯定感にもつながります。すると、だんだんと子どもも「やらされている感」から自発性が芽生えていき、積極的に片付けるようになるでしょう。
子どもの整理・収納を応援!子供部屋の模様替えは家事サポーターへ依頼
子どもが自分で整理・収納できるようになるために、整理収納が得意な人に頼んでみるのも良いでしょう。キッズラインには「整理収納アドバイザー」の資格を持った、片付け上手な家事サポーターが在籍しています。プロとして子どもに「整理の考え方・方法」「収納のコツ」など、丁寧に教えてもらえる良い機会です。
整理収納アドバイザー1級の資格を保有するサポーターにお願いするといくらかかるの?
基本料金¥ 2,100/1時間
※手数料・交通費は含まれていません。
お子様とコミュケーションを取りながら、要不要の分類、動作動線、使用頻度等の確認をしながら進めてくれます。また、根本的に家の整理収納を改善するのサポートを依頼する場合、1回3時間~6時間ほどかかることもあります。根本的な改善や仕組みづくりを希望する場合は、お母様やお父様などもサポートに同席いただくことをオススメします。
まとめ
いかがでしたか?子ども用品の片付けは大人がやってしまえばあっという間ですが、日頃から自分で片付けができるようになると、それだけでも家事が減って楽になりますよね。また、子ども自身が整理収納することができるようになることは、成長過程でもメリットがたくさんあることがわかりました。ぜひ、子どもの年齢にあった生活動線や収納グッズを工夫して、片付けしやすい環境を作ってあげましょう!それでもなかなかうまくいかない時は、整理収納が得意な 家事サポーターへ頼ってみてくださいね!
▼実施中のキャンペーン

▼早速家事代行を依頼してみる

▼あわせて読みたい!家事代行ユーザーインタビュー
家事代行で心に余裕ができ、子供との時間が増えた
家事代行を体験してみたら予想以上の満足感!掃除サポートで家族がお互い優しくなった
週末、もう掃除に追われない。純粋に楽しめる時間を得られた喜び
記事一覧を見る
KIDSLINE TOPページに戻る